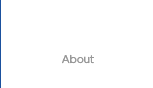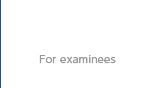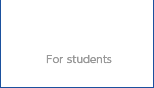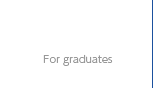埼玉大学工学部 サイエンススクール 〜1日体験化学教室〜
Ⅰ.主催:埼玉大学工学部 応用化学科
Ⅱ.共催:日本化学会関東支部
Ⅲ.日時:令和6年7月27日(土)
Ⅳ.場所:埼玉大学工学部 応用化学科棟2号館2階会議室・23番講義室および実験室
Ⅴ.対象:高校生
Ⅵ.募集人数:40名程度 (各テーマ8名程度)
Ⅶ.参加費:無料
Ⅷ.実験テーマ(概要は下記の項目XIIを参照してください)
1. 見えない物質の検出とヤシ油からセッケンを作成
2. 藍染め・デニムの青い色素インジゴを合成して、ハンカチを染めてみよう!
3. 酵素(生体触媒)の活性を可視化しよう
4. 二酸化炭素を利用する新技術を体験しよう 〜未来の地球を救うためには?〜
5. 茶葉の葉緑素の分離と検出 〜クロマトグラフィーと紫外-可視吸収スペクトル〜
Ⅸ.スケジュール
| 9:15 |
受付開始(会議室) |
9:45 |
学科長挨拶、全体説明と担当者紹介 |
10:00 |
テーマごとに講義・実験開始 |
12:00 |
昼休み(弁当持参推奨) |
13:00 |
実験の続き |
15:00 |
実験終了、アンケート記入 |
15:10 |
学科紹介(自由参加) |
15:40 |
学科内ツアー(自由参加) |
Ⅹ.参加申し込み方法
Ⅺ.注意事項など
Ⅻ.テーマ概要
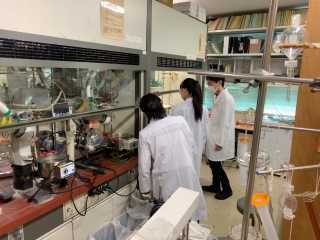

1.見えない物質の検出とヤシ油からセッケンを作成
暗いところでブラックライトを当てると鮮やかな蛍光発色が見えたりしませんか?ブラックライトは紫外線を放出し、蛍光物質を光らせます。薄層クロマトグラフに添加した有機化合物は、通常見えませんが、紫外線ランプを当てると見える化合物があり、検出が可能となります。他の検出法を含めて、見えない化合物の検出を体験してみましょう。また、2つ目の体験では、油脂からセッケンを作成します。椰子の実から採ったヤシ油を油脂原料にします。ケン化反応(アルカリ加水分解)を利用して、油脂をグリセリンと脂肪酸に分解し、セッケン作成を行います。作成したセッケンの洗浄能の評価も体験します。
2.藍染め・デニムの青い色素インジゴを合成して、ハンカチを染めてみよう!
インジゴは現在も非常によく使われている染料の一つで、ジーンズやニット、絣(かすり)や紬(つむぎ)などに愛用されています。インジゴは暗青色の固体で、水やほとんどの有機溶媒に溶けないのですが、還元体のロイコインジゴは水に可溶です。インジゴをロイコインジゴに還元し、その水溶液を繊維にしみこませてから空気中に放置すると、ロイコインジゴは繊維に取り込まれたまま、空気中の酸素で酸化され、不溶性のインジゴに戻り、色落ちしにくい染物となります。本実験では、簡便な合成法でインジゴを合成し、合成されたインジゴを化学的に還元して木綿のハンカチに染み込ませ、ハンカチを青色に染める実験を行います。
3.酵素(生体触媒)の活性を可視化しよう
私たち生き物は、様々な種類の生体分子で構成されており、それらが同時多発的に化学反応を起こすことで、生命活動が成立しています。化学反応を担う分子が酵素と呼ばれるタンパク質です。酵素は、数多くの種類が存在しており、それぞれ特徴的な化学反応を触媒しています。今回の実験では、まず大根を擦りおろして様々なタンパク質が含まれた抽出液を回収します。次に回収した抽出液に含まれるペルオキシダーゼと呼ばれる酵素のはたらきを、特殊な基質を用いて可視化します。この可視化される反応を通じて、酵素の活性や特徴を詳しく調べます。この他にも私たちの研究室で使用する酵素のはたらきを可視化して紹介します。
4.二酸化炭素を利用する新技術を体験しよう 〜未来の地球を救うためには?〜
地球温暖化は、大気中に放出される温室効果ガスが原因で起こっています。その中でも、二酸化炭素は特によく知られている温室効果ガスです。火力発電所や工場、車などから、多くの二酸化炭素が発生します。現代の科学者は、この二酸化炭素を有用な物質に変える方法を研究しています。本テーマでは、電気化学反応装置を使って、二酸化炭素を、社会に役立つ有益な分子に変える実験を体験します。この実験で鍵となるのは「高性能な触媒」です。優れた触媒は、エネルギーや環境問題を解決する切り札になります。当日は、触媒のナノレベルでの構造も観察してもらいます。ぜひ、この体験を通じて、化学の力がどれだけ社会に貢献するかを感じてください。
5.茶葉の葉緑素の分離と検出 〜クロマトグラフィーと紫外-可視吸収スペクトル〜
お茶の葉の成分である葉緑素はクロロフィルという色素です。クロロフィルにはいくつかの種類があり,それらの分子構造はよく似ていますが,色味が異なります。この実験テーマでは,緑茶の成分を抽出し,クロマトグラフィーという方法で成分の分離をします。さらに,各成分の紫外―可視吸収スペクトルを測定し,観察した色とスペクトルを見比べてみます。また,構造がよく似た分子を分離できるクロマトグラフィーという方法について,少し詳しく説明します。